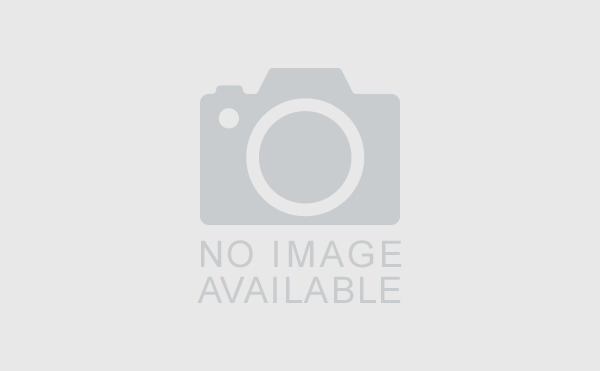高校再編
神奈川県教育委員会は26日の県議会文教常任委員会で、少子化(2027年3月と2031年3月の公立中学校の卒業予定者数を参考)にしてつくられ、県立高校8校を4校に再編・統合する対象校を明らかにしました。対象校は以下の通りです。
(1)舞岡(横浜市戸塚区)+金井(同市栄区)⇒舞丘高校の敷地・施設を利用。
(2)茅ケ崎西浜(茅ケ崎市)+寒川(寒川町)⇒茅ケ崎西浜高校の敷地・施設を利用。
(3)秦野総合(秦野市)+秦野曽屋(同)⇒秦野総合高校の敷地・施設を利用。
(4)上溝南(相模原市中央区)+相模田名(同)⇒上溝南高校の敷地・施設を利用。
茅ケ崎西浜と寒川、秦野総合と秦野曽屋は2030年度、舞岡と金井、上溝南と相模田名は31年度に、それぞれ統合される予定。
また、金井高校に設置されている鎌倉支援学校の分教室は金沢支援学校の分教室として磯子工業の校内に移設される予定。
1978年の100校計画のツケ、というと語弊があるかも知れませんが、21世紀に入ってから、多くの公立高校が再編され廃校になって来ました。卒業生の方々は、お寂しいお気持ちだろうと推察します。
ただこれが時の流れであり、少子化の影響です。個人的な感想ですが、大阪府と神奈川県が相次いで約50年前に行った公立高校の100校計画は、間違いだったと感じます。その時に、私立高校とのうまい住み分けを模索しなかったのだろうか、と不思議です。
高校は義務教育ではありません。誰もが高校に通う状態(1974年に初めて高校進学率が90%を超えた年の筈です)は、認めなくても良かった気がします。
明治維新の時にできた学制では、義務教育は満年齢6歳から尋常高等小学校4年間(後に6年)とされただけです。それでも農家にとっては、大切な働き手が学校に強制的に徴収されるのは、ものすごい抵抗感があったようです。ただしこれによって、日本人の識字率は高いレベルで保たれるようになった訳です。
6年後に更に勉学を志す者のために、5年制の(旧制)中学校がありました。
太平洋戦争後、新制中学校、つまり今の日本国民の殆どが通った中学校ができました。その時に、13歳を中学1年、14歳を中学2年、15歳を中学3年と決め、16歳・17歳は新制の高校生となり、それ以降は教員養成のための師範学校に進学できたようです。だから今も、ご高齢の方の中には、誰それは旧制中学出身と聞くと「勉強ができたのですね」と仰る方もおられます。
改めて言いますが、現在の中学校、新制中学校は、学校組織の中で最もキャリアが浅く、80年は経過していますが、明治以来の歴史はなく、ある意味存在感が、小学校や高校に比べて小さいのです。
これ以上は論を先に進めることは止めておきますが、戦後の30年くらいの発想は、ある意味伸びていく社会、明るい未来しか想定できなかったろうと思います。人口減の考えは、優れた為政者でも持ちえなかったのではないでしょうか?
繰り返しますが、100校計画は間違いだったと思います。学力低下の原因にもなったと思います。この計画が無くなり、入学定員を私立高校と公立高校で1:1くらいに設定しておけば、私立高校の生徒数も多くなって、学費も安くできたように思えます。
結論らしいものが無くて恐縮ですが、ニュースに触れて少し、自分の考えを述べてみました。